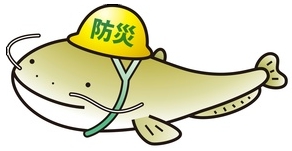皆さんは非常食を備えていますか?
それはどんなケースを想定していますか?
『もし防』では災害発生時に想定される様々なケースを明確にし、各ケースに応じた非常食を専用食品+一般食品で備える方法を今後紹介していきます。
この記事は、その第一弾として防災非常食導入の大枠 ~ どのような食材を どこに どう備蓄するか そのご参考になればと思い作りました。
『防災非常食』とは?
まず「非常食」とは、災害などの非常時に備えて、あらかじめ準備しておく食料のことを指します。
既に災害を意識した備えの意味を含んでいますので、「防災」を頭に付けることにより意味合いが重複します。
ですが、「非常食」には元々天候不順などによる凶作⇒食料危機に備える/対応する、という意味合いも含んでいました。
なので、当サイトでは「防災」をあえて付けることにより地震・台風などの自然災害に対する防災を意識した食料であることを明確にするために『防災非常食』としています。
市販の専用食品を備えて準備OK!?
災害時のための非常食として世の中にはたくさんの商品が出回っています。
一昔前であれば、「かんぱん」や「氷砂糖」などがその代表格でした。

そして今では水やお湯を加えるだけで美味しく食べられるご飯物であったり、長期保存できるチーズケーキであったり、非常時でもそれほどストレスを感じることなく食事ができる災害時のための専用食品も出てきています。
災害大国とも言える我が国日本では、特に平成以降多くの災害に見舞われました。
阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、その他多くの震災や台風・大雨被害。
その中で人々の防災に関する意識が次第に高まり、災害時のために非常食を備えている方も多くいらっしゃいます。
ですが、多くのお宅では、市販の専用食品を購入して備蓄品ボックスに入れて”備え良し!”と満足してしまっているのではないでしょうか。
勿論、専用食品だけでも立派な備えです。
有るのと無いのとでは大違いです。
筆者もいくつか購入して備えています。
ですが、家族全員(ペットも含む)が何日食べられる量?
飽きずにストレス無く食べられるか?
栄養バランスは考慮されているか?
電気が止まったら?
水道が止まったら?
地震で一階が潰れたら?
自宅から避難する時に持っていける?
勤務先で被災したら?
車移動中に被災したら?
と色々なケースを想定したら、沢山の疑問が生まれます。
もし防では、市販の専用食品や一般食品を積極的に活用しつつ、日頃の食事スタイルを防災を意識したものに変えることによって、総合的に防災非常食の質・量・味・対応度を向上させるため取り組みを始めました。
以下にその大枠を示したいと思います。
形態別防災非常食
ひとえに防災非常食と言っても様々なものがあります。
メーカー/販売者が「災害に備える非常食」とうたって販売しているものから、わたしたちが日頃食べており非常食としては認識してないであろう食品まで。
多くの食品がそのままで、または加工して非常食に成り得るということ知って頂きたいと思います。
市販の専用食品
例えば通販サイト「アマゾン」で”非常食 防災”を検索すると3000件以上の商品がヒットします。
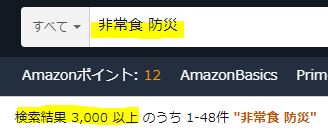
ここ数年で随分と商品が増えてきました。
専用食品の特徴は以下の3点に集約されます。
- 保存期間が長い(3年~)
- 調理の必要が無い
- 常温保存できる
いつ来るか分からない災害に対し備えるものですので、保存期間が短いとイザという時に消費期限切れてた!なんてことになりかねません。
そして、災害で電力・ガス・水道などの生活インフラが止まるケースでも食べられるように、「そのまま」または「水/お湯を加えるだけ」と調理不要であることもポイントの一つです。
当サイトでは市場に無数ある市販専用食品を評価したり紹介することはできません。
興味がある方は、以下のサイトが大変参考になりますのでご覧ください。
はじめての非常食(外部サイト)
市販の一般食品
「災害に備える非常食」とうたっていなくてもそのままで非常食に成り得る食品が沢山あります。
【レトルト・真空パック食品】
カレー、総菜、ご飯など
【缶詰】
肉系・魚系・穀物系・果物系など多数
【乾物】
珍味/鰹節/煮干し(魚の乾物)・昆布・乾燥野菜など
【穀物】
米・麦・小麦粉・パスタ・蕎麦など
【発酵食品】
漬物・ナレズシ・塩漬け魚など
【調味料】
塩・砂糖・醤油・酒・酢など
先に述べた専門食品の様に「長期保存期間」「調理不要」「常温保存」にこだわる必要は無いのです。
保存期間は1年でも良いし、調理要でも良し。
料理が面倒な時に食べるために買ったレトルトカレー、一品増やしたい時のために買ったサバ缶、いつもある米、にしてもそれらのものをある程度分量備えておけば、既に立派な非常食です。
そんな緩い枠組みで考えると、近所のスーパーでは沢山の非常食に成り得るものを売っていることに気が付きます。
一般食品を自ら加工したもの
市販の一般食品を自分で加工して非常食として備えることもできます。
特に、日持ちしない野菜類は、乾燥させたり漬物にすれば長期保存できるようになるのでお薦めです。

肉や魚も塩漬けすれば長期保存できるようになります。
居る場所に応じた防災非常食
当サイトの考え方としては、まず
- 自宅における防災非常食を充実させる。
- 自宅外に居る時でも対応できるようにする。
それをベースとして
これが基本です。
災害の種類や規模にもよりますが、被災地においても避難所へ避難する人よりも在宅避難する人の方が多いでしょう。
自宅に十分な防災非常食を備えておけば、多くのケースは食料に困ることはありません。
その次に、避難所に避難するケースや外出時被災ケースに備えた防災非常食について考えると良いでしょう。
自宅で食べるもの
上記「形態別防災非常食」であげた全ての食料がその対象になります。
日頃の食生活の中で、「生活インフラが止まっても1か月生きられるか?」を目安として食料を調達すると良いでしょう。
各食品の消費期限を把握しつつローリングストック(後に説明)で回していきます。
また食料の保管場所は、地震(1階が潰れる可能性あり)、洪水(1階が水に浸かる可能性あり)被害を考慮して2階にも分散保管しておくと良いでしょう。
避難先で食べるため帯同するもの
「非常時持ち出し袋」「緊急避難セット」等いろいろな名称がありますが、自宅に災害の危険が迫っている時に安全のために避難する、その時に持っていくのが防災セットです。
防災セットには飲料水の他どんな食料を入れておくべきでしょうか。
重要ポイントは、2点。
1.軽く嵩張らない
2.調理を必要としない
非常食専用食品の他、カロリーメイトなどの携帯食、アメ、干し芋、乾燥餅など。
※防災セットが重く大きくなり過ぎないように注意しましょう。
移動中、車内で食べるもの
車移動中に被災するケースにも対応する防災非常食を車内に備えておきましょう。
重要ポイントは、2点。
1.高温環境下でも腐敗・劣化しない
2.調理を必要としない
非常食専用食品の中でも完全に乾燥したもの(ビスケット、乾パンなど)、缶詰、レトルト食品など。
<関連記事>こちらも合わせてご覧ください。
勤務先・外出先で食べるもの
通勤時など公共交通機関を使って移動している時の被災するケースにも対応する防災非常食を備えておきましょう。
重要ポイントは「避難先で食べるため帯同するもの」と同じ2点。
1.軽く嵩張らない
2.調理を必要としない
但し日頃の外出時の話ですので、更なる軽量化・コンパクト化が求められます。
カロリーメイトなどの携帯食、アメ、鰹節、乾燥餅など
<関連記事>こちらも合わせてご覧ください。
ローリングストックを定着させる
防災非常食は保存期間が長いと言っても限度があります。
いつか食べられなくなります。
ローリングストックとは、消費期限が切れる前に、次の備えをした上で食べてしまう。
それを繰り返す(備える⇒次のものを備える⇒古い方を食べる⇒次のものを備える⇒古い方を食べる)ことにより、在庫(食料)を切らすことなく常に一定量以上をキープしておくことを言います。
防災非常食全般においてローリングストックを定着させれば、自宅において常に食料に困らない体制を作れます。
※ローリングストックについては、別記事でより詳しく説明させていただく予定です。
<更新履歴>
2020/08/23 記事公開
<参考文献>
IDP出版「賢者の非常食」発酵学者 小泉武夫著