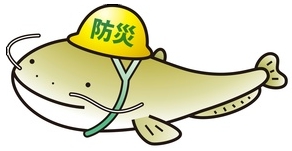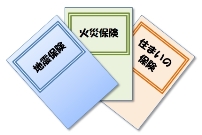台風・大雨などで被災された方々に対しましては、謹んでお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復旧を心より祈念いたします。
この記事は、家屋が浸水被害に遭ってしまった方々のために、できるだけ無駄なく効率よく安全に、また後に影響を残さないような復旧作業方法をお伝えするために作りました。
忘れずに!まず最初にやること
後に公的支援等を受けるために『り災証明書』を市町村役場に発行してもらうことになります。
そのために被災直後の状況を写真に収める必要があります。
早く片付けたい、掃除したい、というはやる気持ちを抑えて、丁寧に以下写真撮影を行ってください。
※日時が記録されるカメラを使ってください。
- 建物の全景(四方から)
- 浸水レベルが確認できるもの(壁に残る水の跡から床までの距離がわかるもの)
- メジャーを使って浸水の深さがわかるように撮影
- 測定場所が確認できるように少し離れた場所から撮影
- メジャーのメモリが確認できる距離からも撮影
- 被害箇所・物の写真(近景と遠景の2枚セットで)
撮影前に作業を行ってしまうと証拠が消滅する可能性があり、り災証明書発行や後の保険請求の障害となるかもしれません。
特に壁に残った泥水跡は重要ですので気を付けてください。
作業前に確認すべきこと
写真撮影が完了したら片付け作業に入りますが、以下の事を確認してください。
- ガス栓を閉め、ガス漏れがないか確認しましょう。
- 浸水による漏電がないか確認できるまでブレーカーは切っておきます。
- 浸水した家屋は細菌・カビが発生しやすく非常に不衛生な状態になっていますので、まず窓を開け放し換気を十分に行ってください。
- 感染症を防ぐためにマスク、丈夫な手袋や靴の着用を心がけ、また服装も肌が出ない長袖・長ズボン等を着用しましょう。
また、浸水した家屋での感染症対策に関しては、以下のページが参考になります。
復旧作業
復旧作業は、被災後早ければ早いほどダメージは少なくてすみます。
筆者は浸水被害後1か月以上経過したお宅で災害ボランティア活動を行ったことがありますが、水を吸った床板や壁などは腐食が進み最早再利用できず、大掛かりなリフォームが必要な状態でした。
早くに作業を行っていれば、そこまで状況悪化することは無かったものと思いました。
但し、住人だけで全部やろうとすると大変です。
ボランティアや頼れる人にお願いしてできるだけ大人数で作業を行うのが理想です。
注:貴重品は安全な場所に移動させておきましょう。
基本的段取り
復旧作業は、基本的に以下の段取り(順序)で行うと良いでしょう。
↓
『床の撤去』
↓
『床下の復旧』
↓
『家屋の洗浄』
↓
『家屋の消毒・乾燥』
↓
『乾燥後の諸々復旧』
以下にそれぞれの作業を詳しく説明していきます。
物の運び出し・分別
廃棄するものと、清掃又はメンテナンスを施して再度利用するものに分けて、屋外へ運び出します。

水を吸って吐き出しにくいもの(布団、ソファー、断熱材など)は、再利用が難しいため基本廃棄となります。
尚、水を吸うと想像以上に重くなるものもありますので気を付けてください。
また、分別のためとは言え、通電して一度水に浸かった電化製品の動作確認するのは止めましょう。
通電することにより破損・発火する可能性があります。
基本的にはメーカーに問い合わせの上、そのアドバイスに従ってください。
<関連記事>家電の浸水被害はどう対応すべきか
床の撤去
和室と洋室に分けて説明します。
和室の場合
畳を全て運び出します(水を吸った畳は基本廃棄)。

畳は水分を含むと非常に重くなりますので無理せず複数人で行ってください。
次にバールで床板を剥がします。
床板の状態が良く再利用できそうなら、割らないよう丁寧に作業を行います。
滑りやすく、また水分を含んで弱くなっている場合があるので踏み抜かないように気を付けます。
また、残った釘やガラス等にも十分注意してください。
洋室(フローリング)の場合
ノコギリやバールなどを使ってフローリング材およびその下の合板(無い場合もある)を剥がしていきます。
その際、更に下にある『根太』を間違って切らないよう注意しましょう。
【フローリング材の再利用について】
水に浸かった時間や材質により異なるので一概には言えません。
ですが、一度水にたっぷり浸かったフローリング材の再利用は難しいと考えます。
仮に物理的再建ができたとしても後にカビの温床になる可能性があります。
もし再利用するのであれば、少なくともフローリング材を分解した状態での充分な乾燥は必要です。
床下の復旧
浸水後は床下に泥や水がたまった状態になっています。
これを撤去し、できるだけ被災前の状態に戻す作業を行います。
床下が土の場合とコンクリート(ベタ基礎)の場合に分けて説明します。
床下が土の場合
- たまった水を抜き、次にスコップ等で泥出しを行います。
※泥が固まってしまうと作業の困難性が高くなりますのでできる限り早く行うのが理想ですが、最悪泥が固まっても土台の土とは色や硬さが違うので見分けがつきます。
全体的に土台の土が見えてくるまで作業を行います。 - 園芸用などの消石灰(粉末のもの)を散布します。
※消石灰は目に入ると大変危険ですので、散布の際はゴーグル、なければメガネを着用するようにしてください。 - 風通しを良くして充分に乾燥させます。(可能であれば扇風機を使うと良いでしょう)
床下がコンクリート(ベタ基礎)の場合
- 水・泥を運び出し、水拭き掃除を行う。
- 希釈した逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)を散布します。
- 充分に乾燥させます。
家屋の洗浄
- 希釈したクレゾール石けん液を浸したデッキブラシ等で外壁・窓・サッシなどを洗浄します。
- 屋内の壁材を剥がし、清掃・消毒・乾燥を行います。
壁内に水を吸った断熱材がある場合は廃棄します。
※浸水程度が軽微の場合、壁に点検口を開けそこから内部を点検、必要な作業を行うことができる場合もあります。 - 台所の裏や下も同様にケアします。
<関連記事>浸水家屋の消毒方法
家屋の乾燥
天気の良い日に、窓を開け放し、しっかり乾燥させます。
電気が問題無く使えるのでしたら、扇風機を使うと更に効果的です。
2015年9月の鬼怒川堤防決壊による住宅浸水被災がありました。
その時の復旧作業および再建工事において充分に乾燥させなかったことにより、後にカビが大繁殖(壁内等)して再度修繕工事を行わざるを得なかった例がいくつもあったようです。
兎に角、時間を掛けて充分に乾燥させることが大切です。
その他諸々
- 住宅再建としての壁・床張り、畳やフローリング敷は専門業者に依頼します。(公的支援が受けられる場合がありますので、役場に相談しながら進めてください)
- 浸水してしまった電気製品に関してはまずメーカーに相談しましょう。
被災者支援としてメーカーによる特別修理対応サービスがある場合があります。
製品名、製品型番、製造番号などを確認してから相談するとよりスムーズです。 - 電気周りは新しくした方が安心です。
一度浸水してしまったコンセントやブレーカーは長期信頼性がありません。
電気工事業者に依頼して交換してもらいましょう。(上記同様公的支援が受けられる場合があります) - 食器や台所用品は、泥落とし、台所洗剤で洗浄後、希釈した台所用漂白剤に漬けて消毒します。
『充分に乾燥』の意味
当記事の文中に『充分に乾燥』と書いているところがありますが、具体的な時間は書いていません。
それは材質や浸水時間などにより、乾燥させる時間が変わってくるからです。
表面的な乾燥状態は目視で分かりますが、吸い込んだ水分を放出し切ったかは目視ではわかりません。
木材であれば木材用の水分計(2千円程度からあります)を使って判断するのも一手です。
【PR Amazon】木材用水分計
(画像をクリックするとAmazonに飛びます)
<更新履歴>
2020/10/17 記事公開
2020/06/30 文言・構成の小変更
※消毒用アイテムは、被災地の役場や保健所にて無償提供してくれる場合がありますので、購入前に一度確認してみましょう。
|
| |
|
| |
|
|